儒学四書の一つである『大学』の思想に基づき、戦前の日本では小学校で「修身」という授業が行われていました。今回は、小学校2年生向けの内容(第4回目)について考えてみます。
※小学校2年生向けの「修身」では、挿絵だけでなく一定の文章が示され、より具体的な考察ができるようになっています。1年生向けの内容と根底は同じですが、より広がりを持たせた内容になっています。
10. トモダチ ニ シンセツ デ アレ
「ブンキチ ガ 大キナ フロシキヅツミ ヲ ソバ ニ オイテ、マツ ノ 木 ノ 下 ニ ヤスンデ ヰマシタ。コタラウ ハ アソビ ニ デタ トチユウ デ、ソレ ヲ ミテ、ブンキチ ニ「ソノ ツツミ ハ オモサウダ カラ、二人 デ モツテ イキマセウ。」ト イヒマシタ。サウシテ ツツミ ノ ムスビメ ノ 下 ヘ タケ ヲ トホシテ モツテ イキマシタ。」
挿絵では、風呂敷包みの下に竹を通して、道を歩いている様子が描かれています。前を進む男の子は、後ろを気にしながら歩いています。
友だちが困っていて、自分が助けられるなら、親切な心で助けようという教えです。世の中では、いつ立場が逆転するかわかりません。自分が困ったときに助けてもらえる世の中を作るためにも、まず自分が親切であることが大切です。
資格取得を目指す人たちは、合格の時期に違いがあれど、同じ志を持つ仲間です。私も受験生のとき、先輩方のブログに励まされました。今、私が自身のノウハウや語呂合わせを紹介するのは、そうした先輩方の行動を受け継ぎ、次にバトンを渡している感覚です。どうぞ遠慮なく、必要なものを活用してください。
11. ブサホフナ コト ヲ スルナ
「ブンキチ ノ ウチ ヘ コタラウ ガ アソビ ニ キテ ヱ本 ヲ ミテ ヲリマシタ。シバラクシテ ブンキチ ハ ハハ ニ ヨバレタノデ、イソイデ ヱ本 ヲ マタイデ イキマシタ。ハハ ハ ヨウ ヲ イヒツケタ アト デ、「モノ ヲ マタイダリ フンダリ スル ヤウナ ブサホフナ コト ヲ シテ ハ ナリマセン。」ト イツテ キカセマシタ。」
挿絵では、母に呼ばれたブンキチが、絵本をまたいで母の方に向かっている様子が描かれています。正座をして絵本を読んでいたコタラウは、ブンキチのその様子を後ろから見ています。ブンキチの母は裁縫か何かをしているようです。隣の部屋からブンキチを呼んだところのようです。
物を大切にする心があれば、たとえ急いでいても、物を踏んだり跨いだりしないはずです。私が意識しているのは、「小さなことを大切にする」ことです。
職場で紙くずが落ちていれば拾います。鞄を地面や電車の床に置かないのも同じです。資格取得を目指すなら、机をピカピカに拭くのも良い習慣でしょう。小さなことにこだわることで、大きな成果につながります。
12. 人 ノ アヤマチ ヲ ユルセ
「コタラウ ハ ノハラ ヘ デテ ブンキチ ノ クル ノ ヲ マツテ ヰマシタ。ソノ アヒダニ ブンキチ カラ カリタ マリ ヲ アヤマツテ 川 ノ 中 ヘ オトシテ ナクシマシタ。ソレデ ブンキチ ガ キタ トキ、ソノ ワケ ヲ ハナシテ ワビマシタ。ブンキチ ハ 「アヤマチ ダ カラ シカタ ガ ナイ。」ト イツテ、ユルシテ ヤリマシタ。」
挿絵には、男の子が二人、小川の辺(ほとり)に立っています。一人の男の子は川の方(毬の消えていった方?)を指さしています。
誰しも過ちを犯します。他人の過ちばかりを責めていると、世の中はギスギスし、平和とはほど遠くなります。自分も過ちを犯すことを考えれば、「許し合う」という視点が生まれます。
資格取得でも、「仕方がないことは許す」と考えると、ケアレスミスを許容しやすくなります。ミスをゼロにするより、得点力を上げることに集中しましょう。
13. ワルイ ススメ 二 シタガフ ナ
「コタラウ ト ブンキチ ガ ノハラ デ アソンデ ヰル ト、四五人 ノ トモダチ ガ キテ、「ツツミ ノ 下 ヘ イツテ アソバウ。」ト サソヒ マシタ ノデ、二人 ハ ツイテ イキマシタ。スルト トモダチ ノ ウチ ノ 一人 ガ 「コヤ ニ カクレテ ヰテ トホル 人 ヲ オドサウ デハ ナイカ。」ト イヒダシマシタ。二人 ガ 「ソレ ハ ワルイ アソビ ダ。」ト イツテ トメマシタ ガ、ミンナ ガ キキマセン ノデ、二人 ハ ワカレテ カヘリマシタ。」
挿絵には、6人の男の子がいて、何か言い合いをしている様子が描かれています。
悪い誘いには乗らず、断る勇気を持つことが大切です。周りに流されるのではなく、自分の信念を持ちましょう。
資格取得の場面でも、無駄な情報や誤った勉強法に惑わされず、自分にとって本当に必要なものを見極めることが重要です。自分の信じる道をしっかり歩みましょう。
14. シヤウヂキ
「松平信綱 ハ シヤウグン ノ ヤシキ デ、ハウバイ(朋輩) ト タワムレテ タイセツナ ビヤウブヲ ヤブリ マシタ。マ モ ナク シヤウグン ガ ソコ ヲ トホリカカリ、「コレ ハ ダレ ガ ヤブツタ ノ カ。」ト トガメ マシタ。信綱 ハ 「ワタクシ ガ ヤブリマシタ。」ト スコシモ カクサズ マウシアゲテ オワビシマス ト、シヤウグン ハ カヘツテ ソノ シヤウヂキナ ノ ヲ ホメマシタ。
シヤウヂキ ハ イツシヤウ ノ タカラ。」
挿絵には、小姓と家臣を連れた将軍が、屏風の前で敗れた箇所を指しながら怒っている様子が描かれています。まだ幼い信綱は、将軍の前で手を付き、頭を下げて、詫びています。その側の二人の朋輩(同じ主人や師に使える同僚・仲間)も正座をして手をついています。
ここでの教えは、上記12.(人の過ちを許すこと)と共通する点があります。過ちを許す文化があれば、正直な人が増えます。今の社会は、他人を非難することばかりが目立ち、責め続ける風潮が強いです。このような環境では、正直者が損をすることになります。その結果、皆が都合の悪いことを隠すような世の中になってしまっています。
資格取得の観点から見ると、最も大切なのは、自分の実力を正直に把握することです。過去問集での「〇×△管理」の判定では、誰からも責められることはありません。だからこそ「正直に△印をつける勇気」を持ちましょう。この習慣は合格にもつながりますし、今後の世の中にも活かせることでしょう。
「けじめをつけよう」という教えについて
ここでの教えは、「親切心、物を大切にする気持ち、許す気持ち、善悪の判断、そして正直さ」—これらを曖昧にせず、きちんとけじめをつけて判断することを重視しています。
資格取得を目指す中では、単に合格点を取ることだけを目指すのではなく、日ごろの些細な行動であっても、自分の将来(合格の先)とどうつながるかを見据えて行動することが大切です。そのようにして進むことで、一見遠回りに思えるかもしれませんが、実は合格への最短ルートであると感じています。
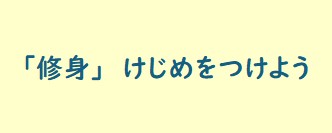
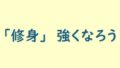
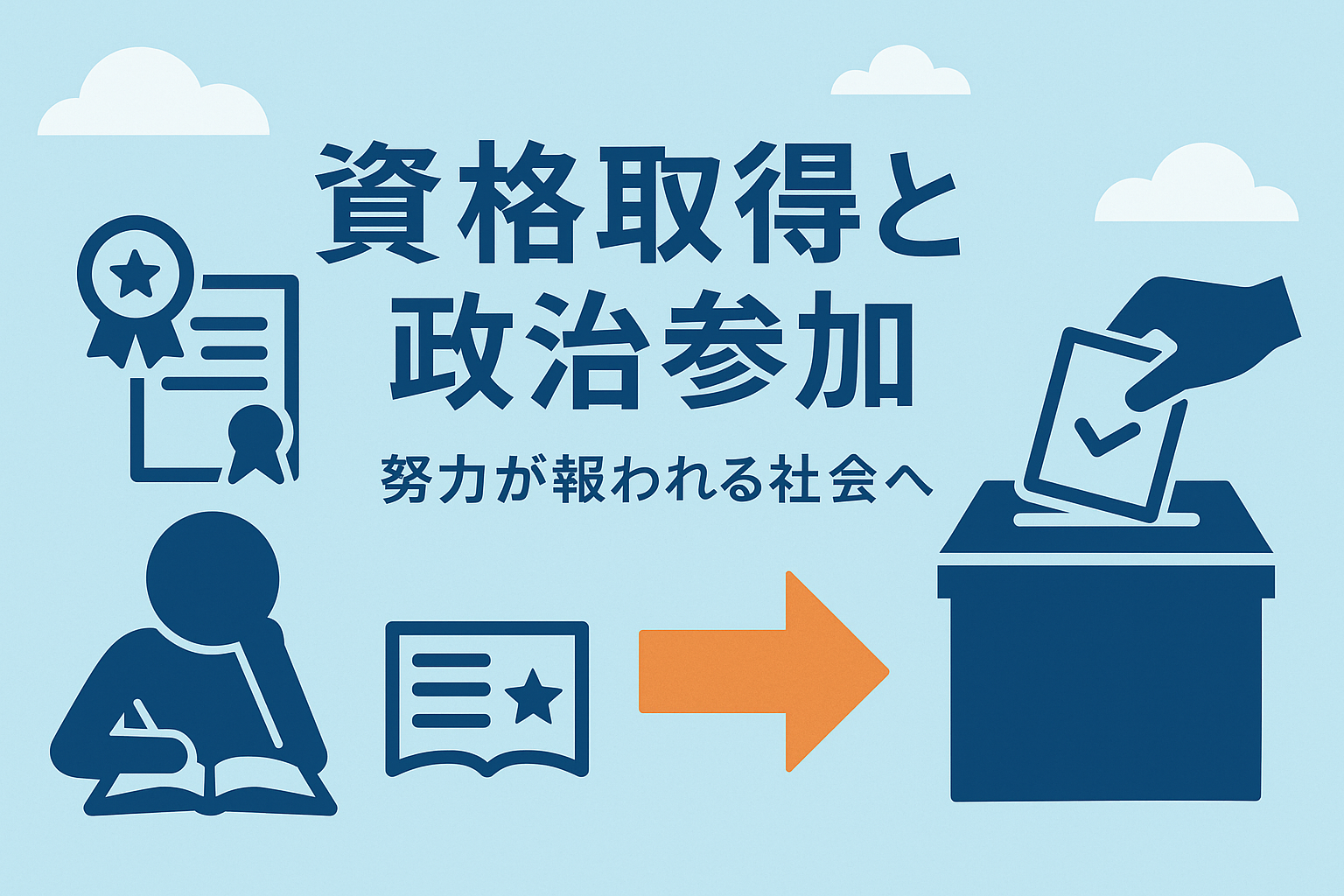
コメント