儒学四書の一つである『大学』の思想に基づき、戦前の日本では小学校で「修身」という授業が行われていました。今回は、小学校2年生向けの内容(第3回目)について考えてみます。
※小学校2年生向けの「修身」では、挿絵だけでなく一定の文章が示され、より具体的な考察ができるようになっています。1年生向けの内容と根底は同じですが、より広がりを持たせた内容になっています。
強くなろう
8. オクビヤウ デ アル ナ
「オクビヤウナ 人 ガ ヤミヨ ニ サビシイ ミチ ヲ トホリカカリ マシタ。カキ ノ 上 カラ ナガイ カホ ノ バケモノ ガ コチラ ヲ ニランデ ヰル ヤウ ニ ミエタ ノデ、大ソウ オドロイテ トモダチ ノ ウチ ヘ ニゲコミマシタ。トモダチ ガ スグ ソノ 人 ト イツシヨ ニ イツテ ミルト、ソレ ハ ヘウタン ガ 下ツテヰル ノ デシタ。」
挿絵では、男が風呂敷包みを落として木の茂みから逃げている様子が描かれています。
9. カラダ ヲ ヂヤウブ ニ セヨ
「二人 ノ キヤウダイ ハ、カラダ ガ ヂヤウブ デ ナケレバ リツパナ 人 ニ ナレナイト ガクカウ デ ヲシエラレマシタ。ソレ カラ 二人 ハ ノミモノ ヤ タベモノ ニ キヲ ツケ、アサ ハ ハヤク オキル コト ニ シマシタ。マタ レイスヰマサツ ヤ シンコキフ ガ カラダ ノ タメ ニ ヨイ ト ヲシエラレ マシタ カラ、二人 ハ ツギ ノ アサ カラ ソレ ヲ ハジメマシタ」
挿絵では、ある男の子が家の外で深呼吸を、また別の男の子が家の土間で冷水摩擦をしている姿が描かれています。もう一つの挿絵は、お日さまがさんさんと昇ってくる様子です。
「強くなろう」という教え
ここでの教えは、単に個人の強さを求めるものではなく、周囲や社会のために役立つ人間になることを重視していたのだと考えられます。
戦前の修身教育では、個人の成長や徳目の習得を通じて、共同体や国家に貢献することが理想とされていました。ここでの教えも、単に自己の利益のためではなく、家族や社会の一員として責任を果たし、困難に立ち向かう姿勢を養うことを目的としていたのだと考えられます。健康であること以上に、強くあることがより周りの役に立つであろうことは想像に難くありません。
現代においても、「強くなる」ことは大切な価値観の一つです。それは身体的な強さだけでなく、困難に立ち向かう精神的な強さ、そして周囲と協力しながら前進する力も含まれます。
資格取得を目指すことも、自己の成長を通じて社会に貢献する手段の一つです。学び続けること、そして努力を惜しまないことが、結果的に自分だけでなく周囲の人々の力にもなっていくのではないでしょうか。
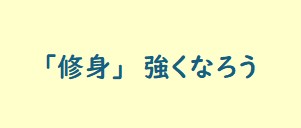
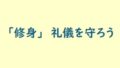
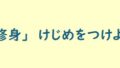
コメント