儒学四書の一つである『大学』の思想に基づき、戦前の日本では小学校で「修身」という授業が行われていました。今回も引き続き、小学校2年生向けの内容について考えてみます。
※小学校2年生向けの「修身」では、挿絵だけでなく一定の文章が示され、より具体的な考察ができるようになっています。1年生向けの内容と根底は同じですが、より広がりを持たせた内容になっています。
礼儀についての教え
小学校2年生向けの修身では、礼儀の大切さが具体的な物語を通して教えられていました。
4. ジブン ノ コト ハ ジブン デ セヨ
「オヤヘ ガ サブラウ ニ ガクカウ ヘ イカウ ト イツタ トキ、サブラウ ハ マダ ヨウイ ガ デキテ ヰマセン デシタ。アワテテ アネ ニ『本 ヤ テチヤウ ヲ カバン ニ イレテ クダサイ。』ト タノミマシタ。ハハ ガ『ジブン ノ コト ハ ジブン デ ナサイ。』ト イヒマシタ。ソレデ サブラウ ハ ジブン デ カバン ノ シマツ ヲ シテ、アネ ト イツシヨニ ガクカウ ヘ イキマシタ。」
挿絵では、母がサブラウに話している様子が描かれています。
5. ベンキヤウ セ ヨ
「ココ ニ 二人 ノ オトコ ガ ヰマス。二人 ハ モト オナジ ガクカウ ニ ヰマシタ。一人 ハ センセイ ノ イマシメ ヲ マモラズ、ナマケテ バカリ ヰタ ノデ、コンナ アハレナ 人 ト ナリマシタ。一人 ハ ヨク センセイ ノ ヲシヘ ヲ キイテ、ベンキヤウ シタ ノデ、イマ ハ リツパナ 人 ト ナリマシタ。
マカヌ タネ ハ ハエヌ。」
挿絵では、帽子をかぶり袴を着てステッキを持った男性と、みすぼらしい格好で木の下に座っている男性が描かれています。
6. キマリ ヨク セ ヨ
「オタケ ハ オキヌ ノ ウチ ヘ アソビニ イツテ、オモシロク アソンデ ヰマシタ ガ、十二ジ ニ チカク ナツタ ノデ、キフニ カヘラウ ト シマシタ。オキヌ モ イモウト モ イマ シバラク ト トメマシタ ケレドモ、オタケ ハ『ゴハン デス カラ、カヘラナケレバ ナリマセン。ゴハン ヲ スマシテ マタ キマス。』ト イツテ カヘリマシタ。」
この挿絵では、オタケが軽くお辞儀をして帰ろうとしている姿が描かれています。オキヌの妹は不満そうですが、オキヌは分かったのか、胸のあたりまで軽く手を挙げてオタケに挨拶しています。
7. ジマンスル ナ
「二ハ ノ オンドリ ガ ケアイ(蹴合い) ヲ シマシタ。一ハ ハ マケテ コヤ ノ スミ ヘニゲコミ マシタ。カツタ ハウ ハ ヤネ ノ 上 ヘ トビアガツテ、イキホヒ ヨク カチドキ ヲ アゲマシタ。コノ トキ 大キナ ワシ ガ トンデ キテ ソノ イバツテヰル ヲンドリ ヲ 一ツカミ ニ ツカンデ イキマシタ。」
この挿絵では、鷲が空からニワトリを狙っている様子が描かれています。※蹴合いとは、ニワトリを闘わせること。
「礼儀を守ろう」という教え
これらの話に共通するのは、「礼儀を守ろう」という価値観です。
「礼儀を守る」とは、単に形式的なマナーを守るだけではなく、自分の行動が相手や社会に影響を与えることを意識し、自らを律して適切にふるまうことが本質です。
ここでの教えは、自己管理を徹底し、自分勝手な振る舞いで他人に迷惑をかけないようにすることを促しています。
これは単なる自己鍛錬ではなく、他者への配慮を前提とした行動規範としての礼儀につながるものと考えられます。
戦前の修身教育では、小学校2年生に対して、これらのことを「礼儀」の視点で教えていたことがわかります。
「自分のことは自分でする」「勉強する」「決まりを守る」「自慢しない」といった行動は、今の時代では個人の努力として捉えられがちです。しかし、当時の教育では、これを他者や社会に配慮し、秩序を守るための礼儀として広く教えていた点が印象的です。
私自身、これまで資格取得を通じて、資格取得と社会・国益とのつながりを意識してきましたが、改めて「他者への配慮を前提とした礼儀」 という視点を大切にし、日々の行動に反映させていきたいと考えています。
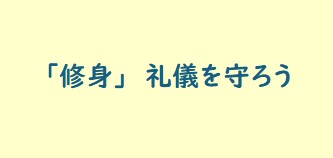
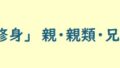
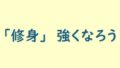
コメント