戦前の小学校教育と資格取得のつながり
儒学四書の一つである『大学』の思想に基づき、戦前の日本では小学校で「修身」という授業が行われていました。これまで、小学校1年生向けの「修身」の内容を資格取得と照らし合わせて考察してきましたが、今回は次のステップとして小学校2年生向けの内容について考えてみます。
小学校2年生向けの「修身」では、挿絵だけでなく一定の文章が示され、より具体的な考察ができるようになっています。1年生向けの内容と根底は同じですが、より広がりを持たせた内容になっています。
親・親類・兄弟に関する教え
1. カウカウ(孝行)
「オフサ ハ チヒサイ トキ カラ 子モリ ナド ニ ヤトワレテ、ウチ ノ クラシ ヲ タスケマシタ。マタ チチ ガ ザウリ ヤ ワラヂ ヲ ツクル ソバ デ ワラ ヲ ウツテ テツダヒマシタ。ソノ ノチ ホウコウ ニ デマシタ ガ、ヒマ ガ アレバ、ユルシ ヲ ウケテ イヘ ニ タチヨリ、フタオヤ ヲ ナグサメマシタ。」
挿絵には、家の土間でお父さんがわらじを作るそばで、オフサが藁を打っている様子が描かれています。
2. シンルヰ(親類との関わり)
「マサヲ ノ ヲバ ガ 子ドモ ヲ ツレテ マサヲ ノ イヘ ヘ キマシタ。マサヲ ノ チチハハ ハ ヨロコンデ ヲバ ヲ ザシキ ヘ トホシ、イロイロ ノ ハナシ ヲ シテ ヰマス。マサヲ モ オモチヤ ヤ ヱホン ヲ ダシテ、イトコ ト オモシロク アソンデ ヰマス。」
この場面の挿絵には、お茶が出され、母親が菓子か何かを持ってくる様子が描かれています。
3. キヤウダイ ナカ ヨク セ ヨ(兄弟仲良く)
「オヤヘ ハ オトウト ノ サブラウ ト ノハラ ヘ イキマシタ。レンゲサウ ヤ タンポポ ヤ スミレ ガ キレイ ニ サイテ ヰマス。二人 ハ ハナ ヲ ツンデ アソビマシタ ガ、サブラウ ノ ツンダ ハナ ガ アマリ スクナイ ノデ、オヤヘ ハ ジブン ノ ヲ ワケテ ヤリマシタ。」
この挿絵では、農村の田園風景を背景に、サブラウがオヤヘから花を分けてもらっている様子が描かれています。二人とも微笑み合っています。
「親・親類・兄弟あっての自分」という教え
これらの話に共通するのは、「親・親類・兄弟があってこその自分」という価値観です。『大学』の修養の考え方は、「まずは個人の修養から」ですが、これらの教えはそこからさらに広がりを持ち、家庭や親類との関わりの大切さを説いています。
私自身も核家族で育ち、現在は妻と二人暮らし。子どもたちは独立しています。しかし、ここ数年で取得した不動産関係の資格は、「人が暮らす場所」にまつわるものです。そのため、たとえ遠方に住んでいても、親・親類・兄弟の暮らしを支えるために活用できると感じています。
資格を活かし、「親・親類・兄弟あっての自分」という視点を持って、身の回りの人々が幸せになるよう努めていきたいと思います。
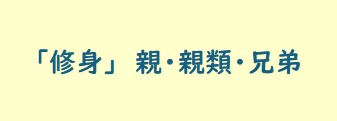
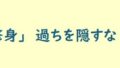
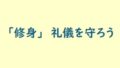
コメント