このブログでは、私が祖母から受け継いだ『修身』の教科書をもとに、「資格取得」というテーマと絡めながら、修身の教えについて記しています。
今回は、小学1年生向けの内容の第3回目です。
※ すでに紹介したように、修身の教科書には、教えとともに挿絵が描かれています。
14. キヤウダイ ナカ ヨク セ ヨ
『修身』の教科書では、お姉さんが弟の草履の鼻緒を結び直してあげる挿絵が描かれています。この場面は「兄弟仲良くせよ」という教えを示しています。
相続などをめぐって兄弟姉妹の間で争いが起こる話をよく耳にします。しかし、家庭内で争いが絶えなければ、国や社会、ひいては世界の平和を望むことは難しいでしょう。まずは身近な家族との関係を大切にすることが重要です。
資格を取得することで得た知識や技術は、兄弟姉妹のためにも活かせるはずです。例えば、法律や税務の資格を持っていれば、家族の困りごとを助けることができます。まずは小さなことから、「兄弟仲良く」を心がけましょう、という教えです。
15. カテイ
挿絵では、家族6人(おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、お姉さん、弟くん)が一緒に食事をしています。特に、一番下の弟くんの話を家族全員が聞いている様子が描かれています。
現代の日本では核家族化が進み、3世代の家族全員で食卓を囲む機会が減っています。筆者の家でも、お正月には娘婿が加わり5人で食事をしましたが、毎日そうするのは難しいのが現実です。
しかし、人数に関係なく、家族と会話しながら食事をする時間は貴重です。資格取得を通じて得た知識や気づきを、遠慮せずに家族と共有してみましょう。同時に、家族の話にも耳を傾け、互いの考えを尊重することが大切です。こうした習慣は、家庭の絆を深め、より良い社会を築く土台となります。
16. テンノウ ヘイカ バンザイ
この項目の挿絵には、天皇行幸の様子が描かれています。江戸城から続く行列の姿が印象的です。また、教科書には「テンノウヘイカ バンザイ」という言葉が記されています。
戦後教育の影響で、多くの人が天皇陛下を「王様」と誤解しているかもしれません。しかし、天皇陛下は単なる権力者ではなく、日本の安寧を天照大御神に祈る「祭祀の主宰者」です。平安時代には摂関政治、鎌倉時代から江戸時代には幕府に統治を委ね、明治以降は近代国家の統治者として位置づけられましたが、その本質は一貫して「日本の安寧を祈る存在」でした。
私たちの幸せを祈ってくださる天皇陛下に対し、私たちもその思いに応えたいと願うのは自然なことです。この相互の関係こそが、日本が世界で最も長く続いている国家である理由の一つです。
「天皇陛下万歳」という言葉は、単なる掛け声ではなく、「日本という国とその民、そしてそれを祈る天皇陛下が、永遠に幸せでありますように」という願いが込められています。資格取得を通じて社会に貢献しようとする気持ちと、天皇陛下を敬う心は、根本的に同じ精神から生まれるのです。
資格取得と『修身』の教えは、一見すると異なるテーマに思えるかもしれません。しかし、資格を活かして家族や社会のために貢献することは、昔から大切にされてきた価値観と共通しています。次回も引き続き、『修身』の教えを通じて、資格取得の意義を考えていきます。
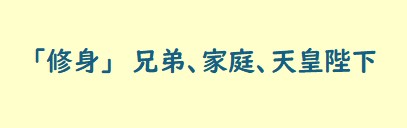
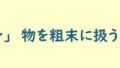
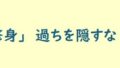
コメント