前回から、このブログでは、私が祖母から受け継いだ『修身』の教科書をもとに、「資格取得」というテーマと絡めながら、修身の教えについて記しています。
今回は、小学1年生向けの内容の第2回目です。 ※前回も紹介したように、修身の教科書には、教えとともに挿絵が描かれています。
10. モノ ヲ ソマツ ニ アツカフ ナ
挿絵には、お弁当箱を投げだして壊してしまった男の子(弟)に向かって、少し年の離れたであろうお姉さんが「物を粗末に扱ってはなりません」と教えている場面が描かれています。二人は向かい合って正座しています。
現代はモノがあふれた時代です。ネットで注文すれば、翌日には欲しいものが手元に届きます。しかし、こうした便利さが「モノのありがたみ」を感じにくくしているのではないでしょうか。
修身の教えは、「モノを大切に扱うことで、ありがたさに気づける人を養う」という逆説の教えとも言えます。これは資格取得の学習にも通じるものがあります。
資格取得の勉強をできることも「ありがたい」ことです。この実感を得るために、勉強道具として鉛筆を使ってみてください。鉛筆は使うほどに先が丸くなり、削ることでまた新品同様の気持ちになります。キャップを使えば短くなるまで大切に使うことができ、そのたびに「モノを大切にする心」を感じられます。

この感覚を大切にしながら、資格取得の勉強に励み、合格へとつなげていきましょう。
11. オヤ ノ オン
挿絵には、父親が男の子の手を引いて、少し離れた学校まで歩いている姿が描かれています。母親は乳飲み子をおぶって、それを見送っています(絵1)。さらに(絵2)では、もう少し幼い子が病床に伏し、両親が看病している場面が描かれています。
人間は、生まれてからしばらくの間、一人では生きていけません。修身の教科書では、小学1年生の子どもに「親の恩」を教え、「今の自分があるのは親のおかげである」と伝えています。
私は、息子が高校生のときに「生んでくれって頼んだ覚えはない」と言われ、ショックを受けた経験があります。しかし、小学校の段階で国全体が「親の恩」を教えることで、より平和な社会が築けるのではないかと思います。
私たちも、親の恩を感じるとともに、資格取得の学習ができる環境や支えてくれる人々に感謝しながら、机に向かいたいものです。
12. オヤ ヲ タイセツ ニ セ ヨ
この項には、長野県伊那市に伝わる「孝行猿」の挿絵が描かれています。
(参考:https://www.cbr.mlit.go.jp/mibuso/siryou_kan/05saru.html )
猿であっても、親を思いやる心は人と変わるものではありません。
親が健在であっても、そうでなくても、自分が資格取得に向けて努力する姿は、きっと親にとって喜ばしいものです。合格した時には、「勉強をがんばったよ」と親に報告し、感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。
13. オヤ ノ イヒツケ ヲ マモレ
挿絵には、母親が「お庭を掃きなさい」と言い、それに応じてウメコとイチラウが「はい」と返事をして、庭を掃除する様子が描かれています。母親自身も縁側を拭いており、結果として家全体がきれいになりました。
親の言いつけを守ることは、自分にとっても、周りの人にとっても良い結果をもたらすという教えです(親にもそれだけのものが求められます)。資格取得の学習も同じです。学習を積み重ね、合格を勝ち取ることが、自分自身の未来だけでなく、支えてくれる人たちにも喜ばれる結果につながるのです。
日々の努力が、良い未来を築く一歩になることを信じて、勉強に励んでいきましょう。
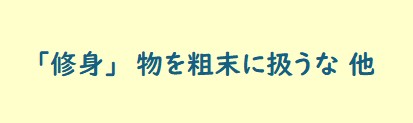
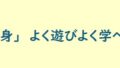
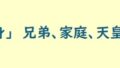
コメント