儒学四書のひとつ『大学』には、平和な世の中を築くためのエッセンスが記されています。日本では徳川時代から広く受け入れられ、その理念が社会に根付いてきました。
平和な世の中を築く(天下治世)には、まず自分の国(領地)をよく治めなければならない。国を治めるには、まず自分の家をよく斉(ととのえ)えなければならない。家を斉えるには、まず自分自身が修養し、立派な人格を作らなければならない。
これは、私が資格取得を通じて考えていることと共通する部分があります。資格を取得した後に、それを家族や会社、社会、さらには国へと活かすことは、単なるスキルの習得ではなく、まず自身の人格を修養しなければ成し遂げられないと考えます。さもなければ、資格は「今だけ・金だけ・自分だけ」の価値観に縛られたものになりかねません。
私は戦後約20年経って生まれましたので、戦前の教育は受けていません。しかし、両親や祖父母、近所の方々から受けた礼儀作法や躾の中には、『大学』から通ずる日本の伝統的な価値観が色濃く含まれていたと感じています。両親は戦後の教育に疑問を抱き、私と兄弟を中学から私立に通わせました。その結果、私は異なる視点から歴史を学ぶ機会を得ました。
例えば、日本の戦争に対する見方にはさまざまな議論がありますが、私は自衛戦争と捉えています。マッカーサーですら『日本の戦争は、経済封鎖により追い詰められた結果の自衛戦争であった』といった趣旨を述べています(1951年5月3日、米国上院の軍事・外交合同委員会の公聴会)。しかし、戦後の教育やメディアの影響で、あたかも日本が一方的に悪であったかのような価値観が植え付けられてきました。私は私立学校に通ったことで、より多角的に歴史を学ぶ機会を得ることができました。
高校1年生のときにアメリカへ1か月間ホームステイをした際、私は実際に人種差別の言葉(イエローモンキー、ジャップ)をホームステイ先の子どもから受けました。世界には綺麗事だけでは動かない現実があり、決して日本だけが悪ということでもないのです。
国同士のぶつかり合いである戦争とは、そもそも軍人同士で戦うものです。しかし、アメリカと連合国は、武器を持たない民間人に対して、無慈悲にも原爆や爆弾を投下しました。その行為は国際人道法の観点からも正当化されるべきではありません(先の大戦では45万人余の民間人が犠牲になっています)。この事実に対する認識が深まらない限り、真の外交関係は築けないとすら思います。戦争の記憶は世代を超えて引き継がれ、歴史を正しく理解し、現在と未来の世代が同じ過ちを繰り返さない努力が求められます。人類は調和を求めて共存していくしかないのです。
このような歴史を背負う私たちが今、最も意識しなければならないことは、『まず自分自身が修養し、立派な人格を作ること』ではないでしょうか。ひとりひとりが修養を積み、それが集合体として家を形成し、国を築き、やがて平和な世界へと波及していくのです。
資格取得は単なる自己研鑽にとどまらず、それを社会や国益に還元してこそ、本来の価値があると考えています。
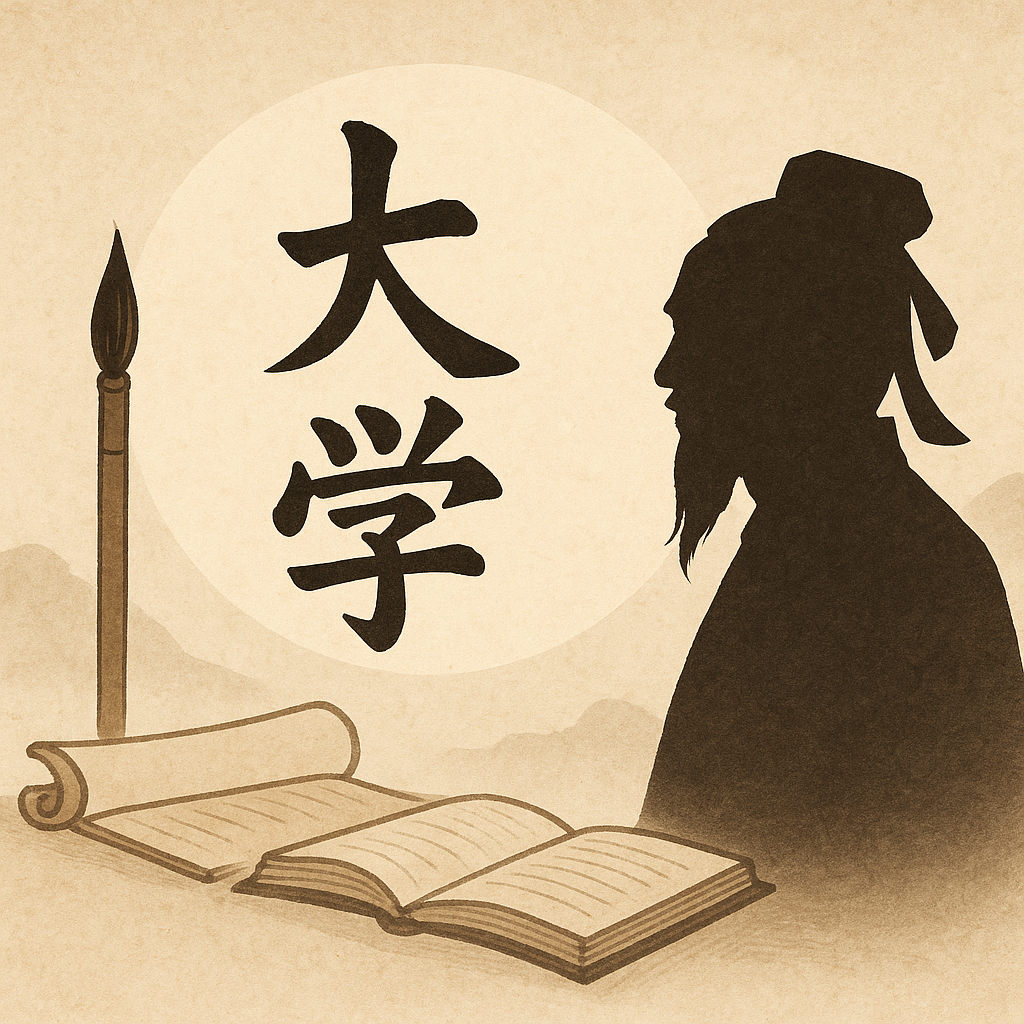

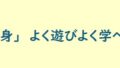
コメント