宅建試験には、受験生を惑わせるひっかけ問題が散りばめられています。実際に私も本番で引っかかってしまいました。
本試験では必ず数問はひっかかる問題があることを前提に、多少ひっかかっても合格基準点を上回るように対策することが重要です。しかし、できることならひっかかることなく、余裕をもって合格したいですよね。
ここでは、ひっかけ問題を回避するための留意点についてお伝えします。
ひっかけ問題への対策
TAC講師のホームルームでのアドバイスや、自分で行き着いたポイントをまとめました。
1. 主語を明らかにして読む
試験時間は決して十分ではありません。ですが、「急いで解かないと!」と思って解くことはネガティブな結果となります。
主語の見落としなどはあってはなりません。「誰が何をするのか?」を正確に把握し、一字一句を適切に読むことが重要です。
2. 何を問われているのかを理解する
問題文をしっかり読んで、何について問われているのかを明確にしましょう。漠然と読んで〇×を判断するのではなく、しっかりとイメージを持ってから、理由とともに解答することが大切です。
3. 慌てずに確認する
覚えた数字や用語が出てくると、「これは知っている!」と反射的に答えを決めてしまうことがあります。しかし、ここがひっかけポイント。慌てず、落ち着いて確認しましょう。
4. 迷ったら他の選択肢も読み直す
特に「どれが誤りか」を問う問題では、一つの選択肢に固執せず、他の選択肢を読み直すことが重要です。正解の選択肢を見つけることで、自信を持って答えられるようになります。
私の実例【宅建・令和5年】
●問3:請負契約
問題文の概要 A(注文者)がB(請負人)に対し、建物の増築工事を依頼した場合に関する問題。
選択肢2
Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
私の判断:〇 → 正解:×
解説 「契約不適合を知った時から1年以内」が正しいのに、本番ではスラッと読んでしまい、誤った判断をしてしまいました。
過去問を何度も解いていたので理解していたはずなのに、本番では相違点に違和感を感じられませんでした(泣)。△印をつけるべき過去問を早期に〇印に格上げしてしまったことも敗因なのかもしれません。加えて思い当たるのは、私は直前予想模試3冊を仕上げられませんでした。日建は3回分中1回で本試験を迎えています。時間さえあれば、やり切りたかったところです。
●問20:土地区画整理法
問題文の概要 土地区画整理法に関する問題。
選択肢4
土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
私の判断:〇 → 正解:×
解説 正しくは「総会の同意」が必要であり、「審議会の意見を聴く必要はない」のですが、過去問で何度も間違えた問題で、カードにまとめて当日も見ていたにもかかわらず本番で間違えてしまいました。
本試験直前期に、×△が5~6回続いている問題については大き目のカードにまとめて繰り返し見るようにしていましたが、その量が多すぎて、十分に整理できなかったことが原因でしょう。やはり、「試験前日までに仕上がっている状態にすること」が理想ですね。
まとめ
宅建試験では、ひっかけ問題が多く出題されます。これに引っかからずに余裕をもって合格するためには、次のポイントを意識しましょう。
- 主語を明確にする
- 何を問われているのか正しく理解する
- 覚えた知識に飛びつかず慎重に判断する
- 迷ったら他の選択肢も見直す
本番では焦りが生じるため、これらを徹底することが合格へのカギとなります。
ひっかけ問題に負けず、確実に合格を勝ち取りましょう!


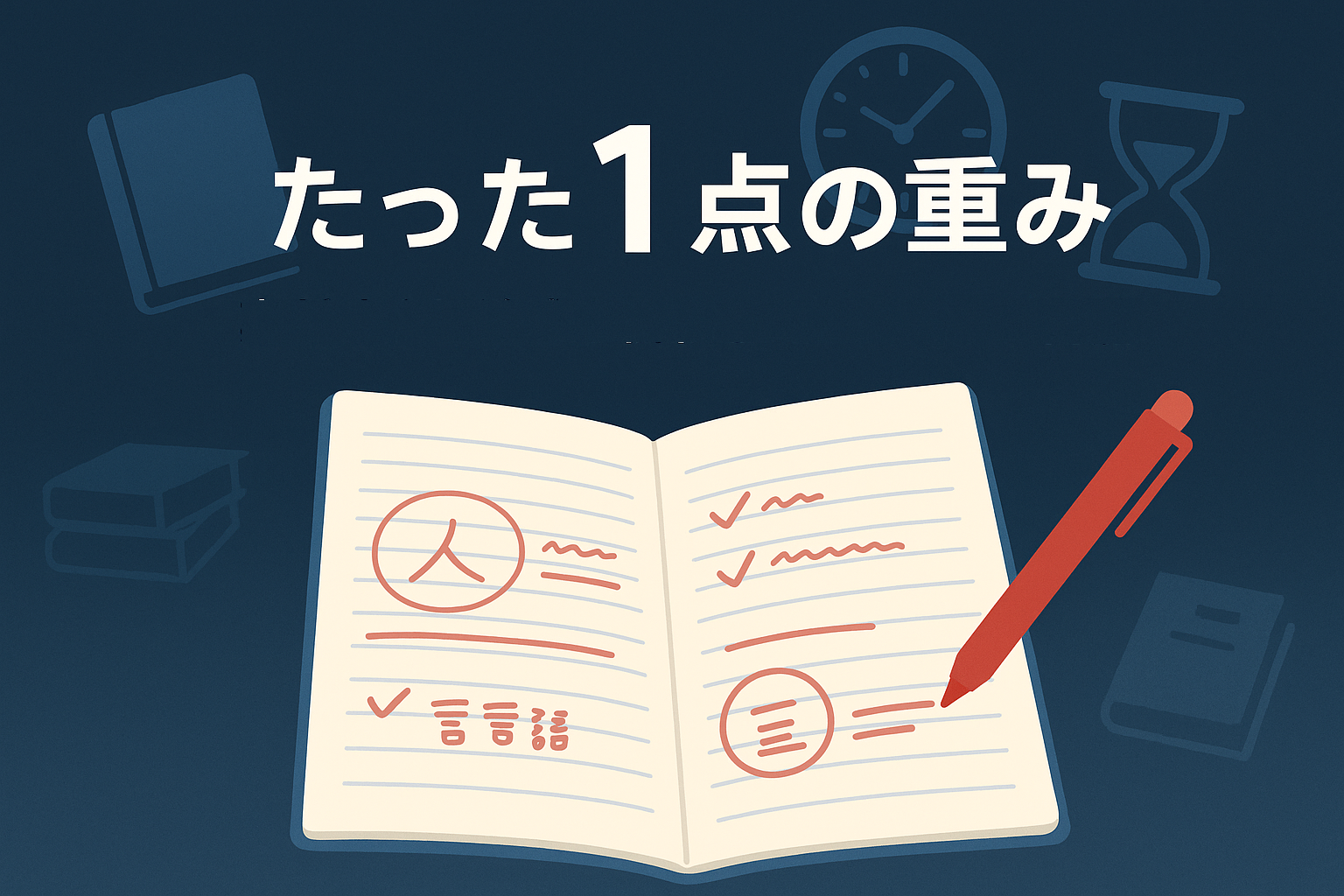
コメント