今日は2025年9月11日。今朝、アメリカ・ユタ州の大学で保守系の活動家、チャーリー・カーク氏(Charlie Kirk)が31歳の若さで凶弾に倒れ、暗殺されるという衝撃的な事件がありました。氏の講演会を最前列で聴講してから、まだ4日も経っていません。あまりにも突然の出来事に、私は深いショックを受けています。
参政党の理念と「大調和」
私は参政党員として活動しており、参政党の理念である「日本の国益を守り、世界に大調和を生む」という言葉に強く共感しています。
これまで私は、この「大調和」とは主に他国との調和を意味するのだと思っていました。しかし今回の事件をきっかけに、むしろ国内外における思想的な対立や誤解の中でこそ、調和を見いだしていかなければならないのではないか、と感じています。
暴力ではなく対話を
立場の違いを暴力で封じる行為は決して許されません。
とはいえ、異なる思想や価値観を持つ人たちと理解を重ねるのは簡単なことではありません。それでも、対話のチャンネルを閉ざさず、冷静に立場を示し続けることが大切だと思います。
現実には安全や法的対応が不可欠ですが、最終的には平和的な対話の積み重ねこそが、真の「大調和」への道につながるのではないでしょうか。
社会を動かす大きな力と草の根の力
世界を動かすものは、思想や言葉だけではありません。経済力や国家権力、巨大資本など、複雑に絡み合ったさまざまな力が影響しています。
その中で一人の市民である私にできることは限られています。しかし、小さな行動や日常の対話を通じて周囲に働きかけることは可能です。
たとえ小さな力であっても、草の根の積み重ねが社会を少しずつ変えていくと、私は信じています。 チャーリー・カーク氏が身をもって教えてくれました。
参政党の特徴について
参政党には、他の多くの政党と異なる特徴があります。それは、大きな支持母体や特定の資金源に依存していないという点です。
党員や支持者一人ひとりが会費を払い、寄付をし、参加費を払ってイベントに参加し、活動を支えています。つまり、「誰かの意向に縛られることなく、国民の声を大切にできる」という点が大きな強みです。 ※明治時代は一定額以上の納税者しか投票権がありませんでしたよね。それを思えば、国を良くするために、ある程度のお金は出せるはず、と自分に言い聞かせています。
この姿勢に共感する人がいる一方で、まだ十分に知られていない部分も多いと感じます。
「学びの党」としての側面
参政党は「学びの党」としても知られています。日常的なメルマガや限定ニュース配信を通じて、学校教育では触れにくい視点や、歴史や社会の新しい切り口を提供しています。
私自身も、「自分の頭で考える」ことを大事にしてきました。
日本は戦争で負けたから悪かったのだ、という単純な歴史観にはどうしてもしっくりこない部分があり、疑問を抱きながら学び続けてきました。戦争とは双方の正義がぶつかるものである――それが自分なりに導き出した答えです。
その疑問こそが、私にとっての学びの出発点となってきました。そして「何かおかしいな」と思うことを一緒に考えられる仲間がいることは、とても心強いことだと感じています。
おわりに
今回の事件を経て、全世界にチャーリー・カーク氏の精神を受け継いだ同志が、何千人、何万人と、誕生しました。私もその一人です。
「大調和」とは単に国際関係の調和を意味するのではなく、異なる立場や考えを持つ人々と、冷静な対話と学びを通して共存の道を探ることなのだと、改めて思います。
国家とは本来、大きな家族のようなものです。その家族の中で仲良くし、助け合い、協力し合わなければなりません。
もちろん、本当の家族(祖父母・親・兄弟姉妹・子・孫)も仲睦まじくあり、互いに支え合うことが大切です。そして家族同士がご近所であれ遠方であれ、私たちは同じ地球という船に乗っています(動植物も、空気も、海も、山も、日光でさえも、一緒に仲良く生きていくべきなのです)。
だからこそ、互いに妥協点を見つけ、ほどよい距離感で付き合い、決して奪い合うのではなく、相互に協力し、戦略的互恵関係を築いていかなければなりません。
日本では、天皇という存在が国民の安寧を日々祈ってくださっています。他国でもその国にふさわしい形で、国民の安寧を祈る存在を置いても良いのかもしれません。
個人主義による資源の奪い合いや争いは、もうまっぴらごめんです。
草の根の活動や日常の小さな関わり合いから、少しずつでも共感や理解の輪を広げていく。やがて本当の「大調和」につながる社会を築くために、私自身もその一歩を歩み続けたいと思います。
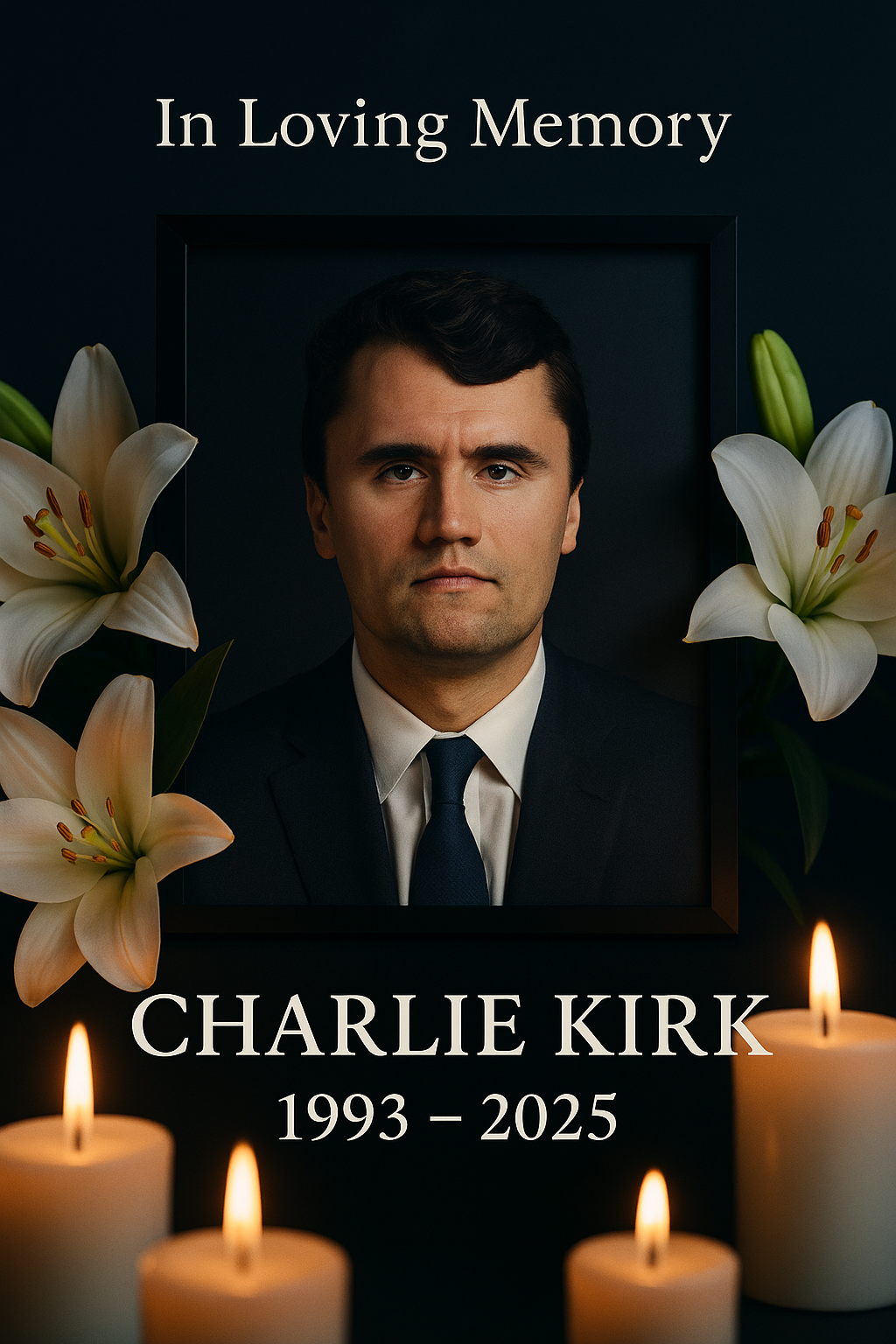

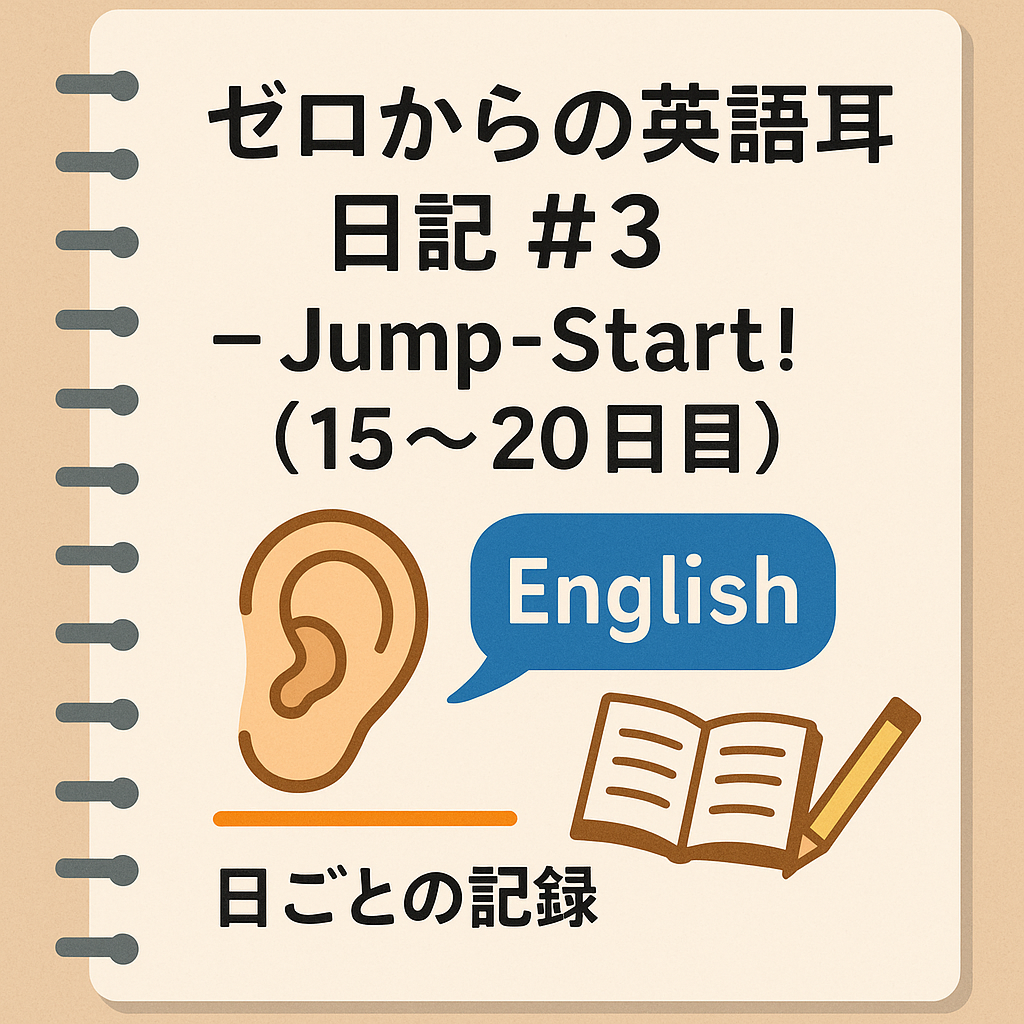
コメント